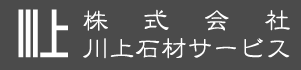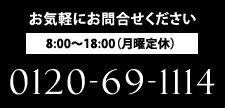お役立ち情報
ここでは豆知識を少しづつ更新していきます。
六曜について
中国から伝わり、江戸時代には民間で使われ始めました。
旧暦の月の始めは六曜が決まっており、先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の順に繰り返されます。
先勝(せんかち、せんしょう、さきかち)
旧暦の1月、7月の1日
急ぐことは吉。午前は吉。午後は凶。
友引(ともびき、ゆういん)
旧暦の2月、8月の1日
友を引く。祝い事は良いが、
葬式などの凶事を忌む。
朝夕は吉、正午は凶。
先負(せんまけ、せんぷ、せんぶ、さきまけ)
旧暦の3月、9月の1日
何事も控えめに平静を保つ日。
午前は凶、午後は吉。
仏滅(ぶつめつ)
旧暦の4月、10月の1日
万事凶。葬式や法事は構わない。
大安(たいあん、だいあん)
旧暦の5月、11月の1日
万事大吉。特に婚礼に良い。
赤口(しゃっく、じゃっく、しゃっこう、じゃっこう、せきぐち)
旧暦の6月、12月の1日
凶日。特に祝い事は大凶。
火の元、刃物に注意。正午は吉、朝夕は凶。
お墓参りあれこれ
■何故水をかけるか
お墓をきれいにするという意味もありますが、仏教における六道(地獄、餓鬼、修羅、畜生、人間、天)の中で、餓鬼世界は乾きに苦しむ世界です。
渇きが癒されるようにという願いを込めた供養の一つという説もあります。
■お願いごとはしちゃ駄目
ご先祖様には、家族のことの報告や、いつも見守ってくれてありがとう、といった、感謝の気持ちでお参りしましょう。
■何故手を合わせるのか
仏教では、対象(この場合ご先祖様)に対する尊敬や崇拝を表現します。
仏様と、自分が一体になるという意味があるそうです。
また、インドでは右手は神聖なもの、左手は不浄なものと考えられ、合わせることによって人間の真の姿になる、と言う説もあります。
■お酒はかけないほうがいい?
故人がお酒好きだったからと、墓石にお酒をかける方もいらっしゃいますよね。
それおは墓石にとってはあまりよくないことなのです。お酒には糖分も含まれていますので、変色したり脆くなったりすることもあるのです。どうしてもかけてあげたい場合は、後で水拭きするなどしてあげてください。
■お供え物は置いて帰っては駄目。
食べ物や飲み物をお供えした場合、帰るときにはきちんともって帰るようにしてください。
なぜなら、カラスが食べ物を狙ってきたり、腐ってしまって汚くなってしまうからです。
他の方のご迷惑にもなりますし、持ち帰って食べることが供養にもつながります。
喪服は何故黒いのか
もともと日本では喪服の色は白でした。白は次の世界への旅立ちの色とされていたのです。
ところが、明治天皇の時代、皇室のお葬式の際、西洋風の黒い喪服を取り入れたことから、喪服は黒いものとされるようになったそうです。
現在でも地域によっては、白い喪服のところもあるようです。
また、仏教の広がりとともに変化したという説や、戦時中、白い服は汚れやすいので黒い喪服になったと言う説もあります。
お墓参りのタイミング
一般的には、お彼岸やお盆がお墓参りをする行事ですが、お墓参りに行く時期は特に決まっているわけではありません。
故人を偲ぶ気持ちが大きくなったとき、
故人と何か話をしたくなったとき、
故人の命日や記念日など、
思い立った時にお墓へ足を運んでみて下さい。
お墓が遠かったり、忙しくて普段は行けないのなら、お正月やお盆などのお休みを利用してお出かけになってはいかがでしょうか。
お彼岸について
■お彼岸てそもそもなんなの?
お彼岸とは、春分の日と秋分の日を中日とする前後3日間、計7日間のことを言います。仏教行事ですが、インドや中国にはなく、日本固有の行事です。
お墓参りをしたり、仏壇を掃除し、お供物をあげたりしてご先祖様を忍び感謝を捧げる週間なのです。
ちなみに法律では春分の日には「自然をたたえ生命を慈しむ日」秋分の日は「先祖を敬い、亡くなった人を忍ぶ日」と定められています。
■「ぼたもち」と「おはぎ」の違いって何?
「ぼたもち」と「おはぎ」の違いを知っていますか?
「牡丹餅」は牡丹の花が咲く春のお彼岸に、牡丹の花のようにちょっと大きめにこしあんで作ります。
「お萩」は萩の季節、秋のお彼岸に萩の花のように小振りで長めに粒あんで作るんだそうです。
ちなみに、夏には「夜舟」、冬には「北窓」なんていう呼び方もあるんだそうです。
■お彼岸の由来
「彼岸」とはサンスクリット語の「波羅蜜多」(パーラミータ)を訳した言葉「到彼岸」が語源になっています。
こちら側の世界を「此岸」といい、遥か西方にある悟りの世界「彼岸」へ渡るという意味だそうです。
太陽が真西へ沈む春分と秋分の日に、六波羅蜜(悟りに至る為の仏教の教え。布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧)を実行し、仏道に精進することが、本来の彼岸の意味なのです。
お盆について
■お盆の由来
「盂蘭盆会(うらぼんえ)」これがお盆の正式名称です。もともとは梵語の「ウラバンナ」を音訳したもので、逆さまにつり下げられる苦しみからご先祖様を救うために供養をするのが、お盆なのです。
■お盆ていつなの?
現在では、8月15日を中心に、一月遅れでお盆の行事を行うのが一般的になっています。(理由としては、新暦が採用される際に、7月では当時一番多かった農家の人が、忙しい時期に当たってしまうからと言う説があります。)しかし、地方によって異なり、東京や都心部では7月13日から16日、地方では8月13日から16日に行うことが多いようです。そのため、8月のお盆には帰省ラッシュが生じるわけです。
また、13日を迎え盆、16日を送り盆といいます。
■お盆にすること
精霊棚(しょうれいだな):マコモのゴザを敷き、位牌を安置し、ホオズキや故人の好きだった食べ物、キュウリで作った馬、ナスで作った牛などをお供えします。キュウリの馬はご先祖様の霊が早く帰ってこれるため、ナスの牛はゆっくりとあの世へ帰るためのお供えです。
迎え火(むかえび):迎え盆(13日)の夕方、ご先祖様の霊が迷わず帰ってこれるように玄関先でオガラに火をつけてたき火をします。火がたけない場合、提灯を灯して迎え火のかわりにすることもあります。
送り火(おくりび):送り盆(16日)の夕方、ご先祖様をお見送りする意味で、オガラに火をつけてたき火をします。
お墓参り:お盆の入りに家族そろってご先祖様の眠るお墓へお参りに行き、ご先祖様を迎えに行きます。
墓石や周りの掃除は前もって済ませておきましょう。